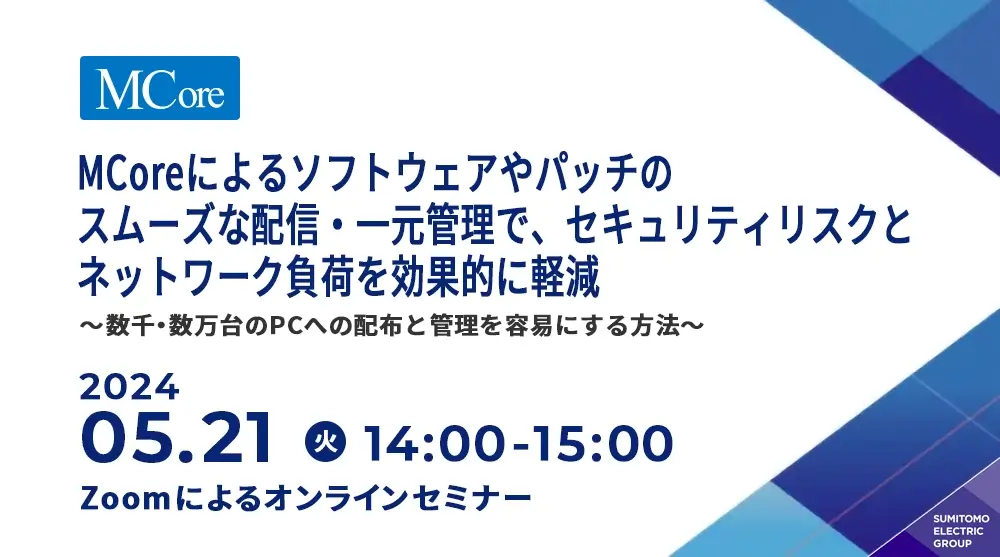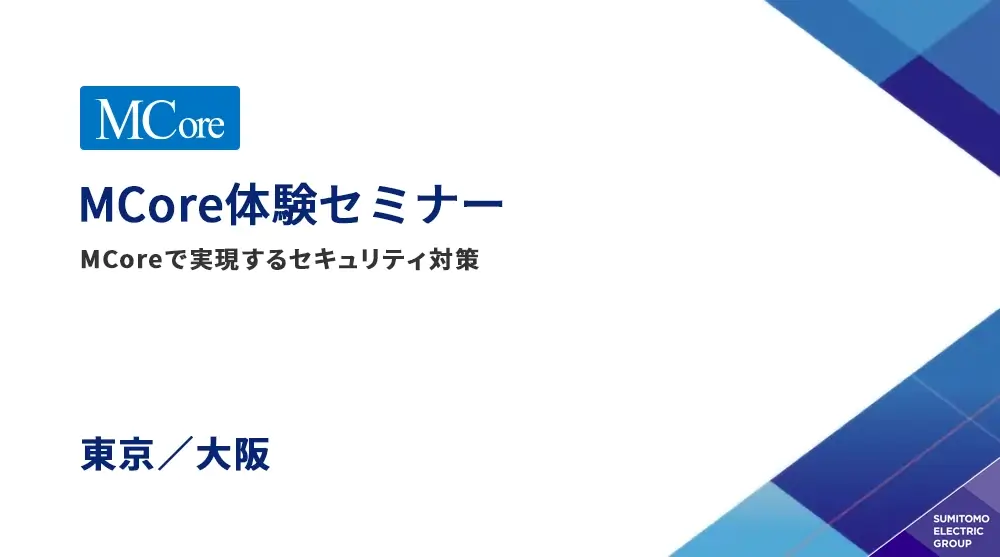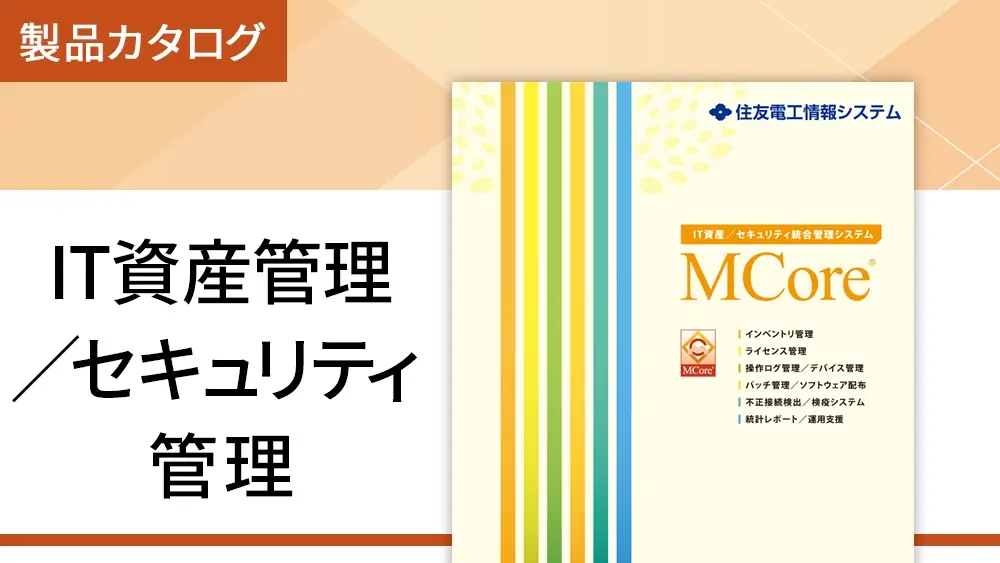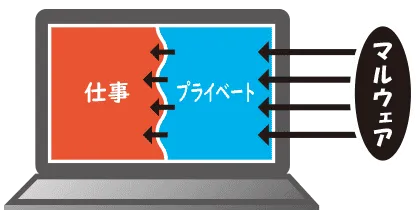テレワークに関する助成金・補助金
導入状況や受け取り時のポイント

情報化社会の加速や新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、日本企業のテレワーク導入率は以前より増加しています。一方で、環境を整えるための資金の調達が難しく、導入を見送る企業が多いのも事実です。
そのような中、国や自治体では、企業のテレワーク導入をサポートできるさまざまな助成金・補助金制度を設立しています。当記事では、テレワークに関する助成金・補助金制度について解説します。
目次
テレワークとは?メリット・デメリットについて
テレワークとは、ICT(情報通信技術)を用いて、オフィスから離れた場所で働くことです。ICTを用いた在宅勤務やサテライトオフィス勤務、さらにはカフェなどでの勤務などが当てはまります。
テレワークに関する情報は、厚生労働省、総務省の「テレワーク総合ポータルサイト」でも発信されています。
ICTとは?
「Information and Communication Technology」の略で、ITの技術を利用した情報伝達のための技術を意味します。
身近なものであれば、スマートフォンを利用した会話や、オフィス外で作成した資料の社内システムへの送付、SNSでのコミュニケーションなども、すべてICTを活用したものです。
ITが技術そのものを表すとするなら、ICTは「ITの技術をどう活用して情報交換やコミュニケーションを成立させるか」に焦点を当てた概念といえるでしょう。ICTは日本政府での正式名称としてでなく、世界中で使われている言葉です。
リモートワークとの違い
テレワークとリモートワークは、ビジネスシーンにおいては同じ意味で使われることが多いです。しかし厳密には、「ICTを使うか否か」によって使い方が変わります。
リモートワークは、ICTの有無に関係なく、オフィスから離れた場所で働くことです。一方でテレワークは、原則としてICTを使った業務を意味します。リモートワークという大枠に、テレワークが含まれるイメージとなります。
とはいえ、無理に使い分ける必要はありません。相手の呼び方に合わせれば問題ないでしょう。
テレワークのメリット・デメリット
企業がテレワークを導入するメリットは次のとおりです。
- 従業員の通勤時間削減による生産性向上
- 育児や介護、その他の用事などのさまざまなライフスタイルへの適応による、従業員のエンゲージメント向上
- 非常事態発生時への対応力向上(災害時の事業継続など)
- テレワーク導入のアピールによる新しい人材の確保や離職防止
続いてデメリットは次のとおりです。
- 管理業務の煩雑化によるコスト増大
- 従業員同士のコミュニケーション機会減少による生産性低下
- オフィス外のセキュリティの弱さによる情報漏洩やウィルス感染などのリスク増加
実際に導入して効果があるかどうかは、業務内容や従業員が望むワークライフバランスなどによっても変化します。
導入前には、従業員の意見、業務フロー、取引先との関係、予算などについて、社内でヒアリングと検討を行いましょう。

2022年度のテレワークの導入状況について
テレワークの導入率は、2020年~2021年にかけて大きく増加しました。総務省の「令和3年 情報通信白書」を見ると、2020年3月~2021年3月の間で、テレワークの実施率が約2~3倍となっています。
2022年においては政府の緊急事態宣言の解除もあり、2021年と比べると、テレワークを実施する企業は減少傾向です。とはいえ、一度導入した後もテレワークを継続する企業も多く、テレワークは徐々に普及しつつあります。
例えば、東京都が発表する「テレワーク実施率調査結果(2022年4月)」によると、従業員数30人以上の都内企業でのテレワーク実施率は52.1%と、2020年4月の24.0%と比べて2倍以上増加しています(2022年3月は62.5%)。
パーソル総合研究所の調査でも、2020年3月と比較して2022年2月時点ではテレワーク実施率が、どの従業員規模においても2020年4月の急上昇から実施率を維持しています。
| 従業員数 | 2020年3月 | 2022年2月 |
|---|---|---|
| 10~100人未満 | 7.7% | 15.4% |
| 100~1,000人未満 | 12.6% | 26.1% |
| 1,000~10,000人未満 | 18.1% | 39.9% |
| 10,000人以上 | 22.0% | 46.9% |
また、同調査ではテレワークを継続してほしいと答える従業員が80%を超えていました。
以上のことから、企業のテレワーク導入の流れは、今後とも継続すると予想されます。しかし、テレワークを導入するには、さまざまな問題点をクリアしなければなりません。
テレワーク導入において企業が抱える問題点とは?
企業によるテレワーク導入の流れは進んでいるものの、全体的に見ると普及しきっているとは言い切れない状況です。導入に関しては、次の問題点があります。
- 業種や業務内容自体がテレワークに適さない(サービス業や運輸業など)
- テレワークでの業務進行が困難な仕事だから
- セキュリティ面で不安があるから
- 文書作成・承認・共有などの面で電子化が進んでいないから
- テレワーク環境やITツールを整えるための資金が足りないから
とくに中小企業の導入率は、大企業と比べると低いのが現状です。業務内容もさることながら、「大企業ほどテレワークの環境が整っていないこと」「整えるための資金に余裕がないこと」が要因として挙げられます。
もしテレワーク導入に際し、資金面の問題がある場合は、テレワーク関係の助成金や補助金を利用するとよいでしょう。

テレワークにまつわる助成金・補助金とは?
国や自治体では、主に中小企業・小規模事業者を対象とした、助成金・補助金制度を設立しています。その中で、テレワークに関する環境整備などにかかる経費を対象とするものがあります。
要件を満たせば、数十万円~数千万円レベルかつ、返済不要の資金調達が可能です。
助成金と補助金の違いは次のとおりです。
| 支給される資金 | 概要 |
|---|---|
| 助成金 |
|
| 補助金 |
|
対象となる経費は、主にテレワークに関する新しい設備・システム・備品の導入、新規人材の確保、既存人材の離職防止などに関するものです。
助成金・補助金の種類・内容
テレワークにまつわる助成金・補助金を、それぞれ2種類ずつ解説します。解説するのは、2022年7月時点での公募のあるものに限ります。
テレワーク関連の助成金
テレワークにまつわる助成金は次のとおりです。
- 人材確保等支援助成金
- テレワーク促進助成金
人材確保等支援助成金(テレワークコース)
人材確保等支援助成金(テレワークコース)とは、良質なテレワークを制度として導入・実施し、人材確保や雇用管理改善などの効果をあげた中小企業を対象にした助成金制度です。
就業規則や労働協約などの作成・変更、通信機器などの導入・運用、Web会議やクラウド系サービスなどにかかる経費が対象になります。
「機器等導入助成」は支給対象となる経費の30%、「目標達成助成」は経費の20%まで支給されます(上限あり)。
厚生労働省 人材確保等支援助成金(テレワークコース)テレワーク促進助成金
東京都は、感染症拡大防止と経済活動の両立に向けたテレワーク定着を目指す企業を対象にした、テレワーク促進助成金制度を設立しています。
規模が2~30人未満の事業所は助成率1/2・助成限度額150万円、30人以上~999人以下の事業所は助成率2/3・助成限度額250万円が支給されます。
2022年は一般コースに加えて、非正規社員にテレワークを対象とした非正規社員拡充コースが新設されました。申請受付期間は、令和4年5月9日(月)から令和5年1月31日(火)です。
公益社団法人 東京しごと財団 テレワーク促進助成金(令和4年度)テレワーク関連の補助金
テレワークにまつわる補助金は次のとおりです。
- IT導入補助金
- ものづくり補助金
どちらもテレワーク関係以外の経費も対象にできるので、必要に応じて申請内容をご検討ください。
IT導入補助金
IT導入補助金とは、ITツールを導入することで業務効率化や売上アップなどを目指す、中小企業や小規模事業者を支援する補助金制度です。
ソフトウェアの購入費やクラウド利用料などの一部が補助されます。補助金の限度額はコースによって、20万~450万円と変化します。
IT導入補助金2022ものづくり補助金
ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)とは、2022年以降で導入される制度(働き方改革やインボイス制度など)に対応するための改善を支援する補助金制度です。通常枠をはじめ、さまざまなコースがあります。
一般枠でも補助金額は750万~1,250万円と、支給額が大きいのが特徴です。
公式サイトの「ものづくり補助金総合サイト」のデータポータルにて、状況ごとの採択率がデータ化されています。成果事例の紹介のページとともに、申請時の参考にするとよいでしょう。
ものづくり補助金総合サイトその他都道府県・自治体ごとのテレワーク助成金・補助金等一覧
全国や東京都の企業が対象のもの以外にも、都道府県・自治体が独自に設定する助成金・補助金・その他支援金もあります。例えば2022年7月時点では、以下の種類が存在します。
- 山梨県:オフィス移転等に対する新たな助成制度
- 北海道冨良野市:ワーケーション実証費用助成金
- 秋田県:リモートワークで秋田暮らし支援金、ワーケーション実施団体奨励金
- 茨城県筑西市:筑西市サテライトオフィス等開設支援事業補助金
- 兵庫県:テレワーク導入支援助成金
ここで紹介した以外にも、地域ごとでさまざまな支援制度が整えられています。どのような制度があるか、一度自治体に問い合わせてみてください。
助成金・補助金を受け取るためのポイントは?
助成金・補助金を受け取るために必ず注意すべきポイントは、各制度の公募要領に書いてある支給要件を満たすことです。
いくら企業の業績が悪かったり、生産性向上が見込める事業計画書を作ったりしても、支給要件と合致しなければ支給を受けられません。
例えば、第11次締切分ものづくり補助金には、次の基本要件が設定されています。
【基本要件】 以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定していること。
引用:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(11次締切分)
- 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加。(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
- 事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。
- 事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加。
公募要領には他にも、応募の締切や必要書類など、満たすべき項目がすべて記載されています。必ず目を通しておきましょう。
また補助金に関しては、加点項目が設定されているものがあります。基本要件とともに加点項目をクリアすると、採択される可能性が上がります。複数の加点項目をクリアするか否かで、採択率が大きく変わるという公式データもあるため、できる限り条件を満たせるように意識してください。
ときには中小企業診断士や社会保険労務士、認定経営革新など支援機関の助成金・補助金の専門家への依頼も検討するのがよいでしょう。

テレワークに関する助成金・補助金で労働環境を整えよう!
資金不足でテレワーク導入が難しいという企業は、助成金・補助金を活用することで解決できるかもしれません。支給要件に当てはまる、または要件を満たせる事業計画がある場合は、申請をおすすめします。
弊社住友電工情報システムの「MCore」などのITソリューションであれば、助成金・補助金の支給要件の経費として申請が可能です。機能も充実しており、業務効率化やセキュリティ強化など、企業の課題解決にも寄与できます。
デモ機貸出やセミナー開催なども行っているため、ぜひ一度ご相談ください。
【関連記事】
-
働き方改革推進のため勤務状況を把握したい
https://www.sei-info.co.jp/mcore/column/telework/ -
強固なセキュリティ対策をしたい
https://www.sei-info.co.jp/mcore/column/strong-security/ - 情報漏洩対策
https://www.sei-info.co.jp/mcore/column/security/ - テレワークを行う際のセキュリティ対策まとめ!
https://www.sei-info.co.jp/mcore/column/telework-security/
【参考文献】
-
「令和3年 情報通信白書」(総務省)
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd123410.html -
都庁総合ホームページ「2022/05/16 産業労働局 報道発表資料」
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/05/16/09.html -
パーソル総合研究所「第六回・新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」
https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/assets/telework-survey6.pdf -
厚生労働省ホームページ「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html -
公益社団法人 東京しごと財団 「支援事業(助成金等)について テレワーク促進助成金(令和4年度)」
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/telesoku.html -
サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局ポータルサイト「IT導入補助金 事業概要」
https://www.it-hojo.jp/overview/ -
ものづくり補助金総合サイト
https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html -
ものづくり・商業・サービス補助金事務局 (全国中小企業団体中央会)
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(11次締切分)」
https://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/ippan/11th/reiwakoubo_20220513.pdf